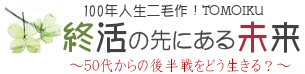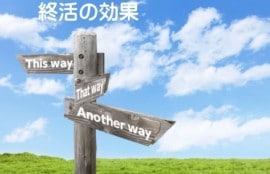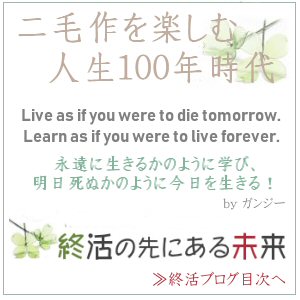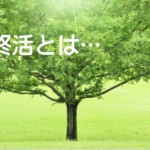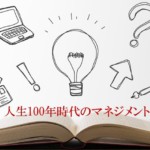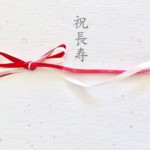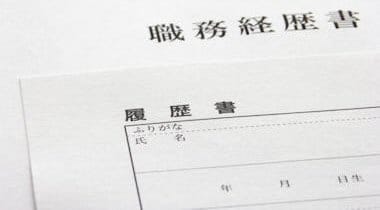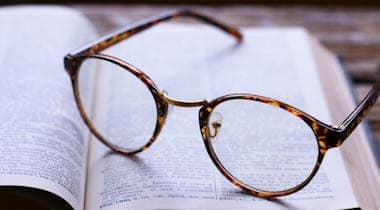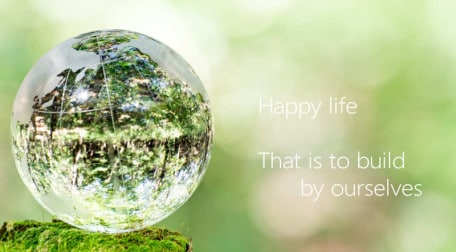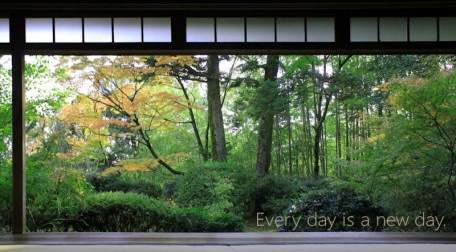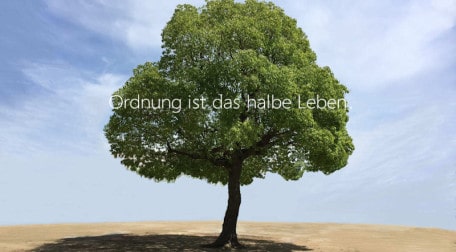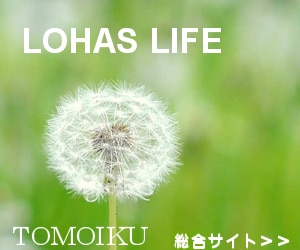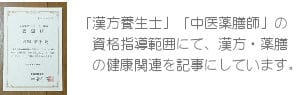終活はまだまだ先…と先送りをしていると、自分で想定していなかった状況を乗り切ることができなくなることが考えられます。
体が衰えると実行が難しくなりますし、認知症になれば伝えたい思いが届きません。
生前整理には、ある程度の時間と体力が必要なので、元気なうちに始めることをお勧めします。
終活にははじめるタイミングがあります。
代表的な10のタイミングを取り上げました。
目 次
- 1 不安な気持ちに目を背けない対策に「終活」を利用
- 2 終活を始める10のタイミング
- 2.1 終活を始めるタイミング1:人生の節目(50.60歳の誕生日・還暦などの長寿祝い)
- 2.2 終活を始めるタイミング2:定年退職した時
- 2.3 終活を始めるタイミング3:病気になった時
- 2.4 終活を始めるタイミング4:体に老いを感じた時
- 2.5 終活を始めるタイミング5:大切な人を亡くした時
- 2.6 終活を始めるタイミング6:年金・金融の法改正や会社の体制が変わった時
- 2.7 終活を始めるタイミング7:周囲からもめた事例を聞いたとき
- 2.8 終活を始めるタイミング8:親が最期を迎え相続問題が発生したとき
- 2.9 終活を始めるタイミング9:子や孫・友人に勧められた時
- 2.10 終活を始めるタイミング10:テレビや雑誌の特集やエンディングノートに興味を持った時
- 3 終活は家族や関係者と協力
- 4 終活をはじめる3つの心構え
- 5 おすすめ記事
不安な気持ちに目を背けない対策に「終活」を利用

日経ビジネス「サラリーマン終活 定年後30年時代の備え方」で、約1800人を対象(30~70代以上)に、退職後の生活に関するアンケート実施したところ、「あらゆることが不安」という声が多かったとのこと。
加齢とともに増す健康面への不安や家計に関する不安など、定年退職後の自分の姿を想像すると、不安を持つ人が多いとのことでした。
サラリーマンに限らず、実際には多くの人が漠然とした不安を抱えているのがわかります。
その不安な気持ちに対して準備に着手できていないのが現実です。
重要なのはしっかりした計画や準備だけではありません。
その中から、生きていく上で何を糧としていくのか…と、心を整理して心のあり方もあなたの幸・不幸を左右します。
独身で人生を貫いている方の覚悟とは違い、1人になることを想定していなかった夫婦の場合、自分におかれた環境の変化に、柔軟に気持ちを切り替えていかなければなりません。
どんな状況になったとしても、人生は続きます。
心が豊かで生活にメリハリをつけながら、自分のやってみたかったことや趣味などで、生涯、生き生きと汗を流していくことが、人生二毛作…100年時代の生き方です。
不安なことを避けることなく対策を考える1歩として、終活があると考えてみましょう。
終活を始める10のタイミング

では終活はどのタイミングではじめるのか。
少子高齢化の進む日本だけではなく、海外でも多くの人が終活に取り組んでいます。
先進国では、「穏やかで充実した老後」が目指されているのがわかります。
しかし、終活を始めるタイミングが掴めず、「どうしよう…どうしたらいいか…」と考える時間だけが経過してしまうケースも少なくありません。
終活は、早く始めるに越したことはありません。
子どもの人数が確定されたり、家のローンを見直したり、親の老後問題を考えたり、自分の生涯年収が見えてきた40代から終活に取り込んでいる人もいます。
しかし、何かきっかけがないと始めにくいのも確かだと思います。
最終的な終活を始めるのに適した時期を見ていきます。
終活を始めるタイミング1:人生の節目(50.60歳の誕生日・還暦などの長寿祝い)
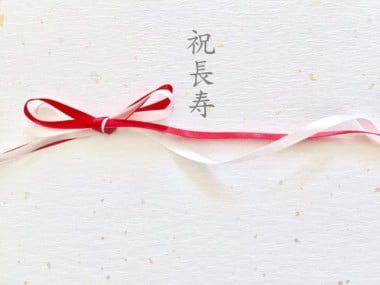
定年退職を意識した50代で、今後の不安を感じる年齢で、誕生日や還暦などの長寿祝いで、人は「人生」について思い返したり、今後を想像したりします。
それは伴侶も同じで、今後の収支が心配になるのは人の心理です。
そのような人生の節目に、様々な想いや不安を書き出すことで、対応するべきことが明確になります。
人生の節目に、過去を思い起こし、未来を考える終活のタイミングにしてはいかがでしょう。
終活を始めるタイミング2:定年退職した時

定年退職した時期は、終活を始める最終的なタイミングです。
できることなら、退職する前が今後の見通しがはっきりするので、再就職をすべきかどうかの対策を練る終活を進めておくことが理想です。
自分が生きていく分には資産の心配がなく、相続に関して心配事がある方にとっては、最高のタイミングになります。
時間の余裕ができるので「これからどうするの?」と聞かれ、仕事をする必要がなくなった今後の過ごし方を考えていくと思います。
終活は、空いた時間をどのように活用して生きていくのかを考えるのに最適です。
終活を始めるタイミング3:病気になった時

いつまでも健康で生きているのが一番です。
しかし、突然具合が悪くなる心配や、生死の境をさまよった経験のある人は、死は突然くる可能性があることを強く意識しています。
もし死んでしまったら、家族はどうするのだろう…葬儀は誰を呼ぶのだろう…遺産相続は…
隠れ資産や隠れ借金を持っている方は、早々に対策を考えるべきです。
病気になって不安を抱えたままの治療は心身共に良いことはありません。
そんな時は、「いい機会」と考え、家族に終活について話し合い、進めていきましょう。
ネガティブになるのではなく、後に健康になる病気であったとしても、真剣に死と向き合うことで、しなければならないことが見えてきます。
ただし、余命宣告を受けた場合、悲観的になって衝動的な行動には注意しましょう。
余命宣告はあくまでも目安であって、余命宣告を受けたからと言って、その通りの未来がやってくるわけではありません。

私の知り合いで、余命宣告を受けた方のお話です。
生命保険の特約のリビングニーズを利用して、死亡保険金を前もって受け取り、動ける残りの人生は“旅”をすると言って、出かけていきました。
その旅行がよかったのでしょうね…。
夫婦で自然を楽しみ、美味しいものを食べ、穏やかで幸せな時間が多かったのでしょう。
旅から帰ってきた3カ月後の検診で、ガンが消えてしまったのです。
このように、予測を超えて生存するケースは珍しくありません。
余命宣告で悲観的になって財産をすべて処分してしまうなどの、極端な行動はトラブルの元になるので、気をつけるようにしましょう。
終活を始めるタイミング4:体に老いを感じた時

病気として健康診断で発見されてはいないけれど、歩いていただけなのに息が上がってしまうなど、普段から体を鍛えることを意識した行動を起こしていない場合、謙虚に“老い”は体で感じてしまいます。
ひとりで生きている方は、もしもここで倒れたら、誰がみつけてくれるのか…と考えることもあると思います。
体の老いを感じ、不安な気持ちがあるのであれば、申し送りとしての「終活」を考えてみましょう。
70や80歳以上になると、両親を心配した子供から「今後どうするの?」という質問もあるかもしれません。
子どもと同居なのか?施設なのか?
いずれにしても、終活のひとつである生前整理を始めてみましょう。
部屋に不要なものを、一度に片づけるのは大変です。
自分が所持していたものなのですから、自分で処分していくことが、残された者にとっては嬉しいことだとも思います。
終活を始めるタイミング5:大切な人を亡くした時

日本人の平均寿命を考慮すると、70代以上になると配偶者に先立たれてしまうケースが多く、多くの人は50代~60代で親の死を経験することになります。
50代の同窓会では、病気で旅立った友達の話も聞くようになります。
大切な家族や人の死は、「自分もいつかは来る」と思い、悲しみの中から命の重みを教えてくれます。
その時こそ、自分自身の死と向き合ういい機会です。
親や配偶者の死を経験すると、葬儀を行うにあたり、どのくらいの規模で誰に声をかけていくのがいいのか…と悩み、悲しむ時間よりもそのことに時間を費やしてしまうことも多いです。
その後の遺品整理や相続と、わからないことが多いので、調べながらの作業になります。
経験したことがある方は、その困ったことを自分の終活では解決しておきましょう。
親や伴侶が他界すると、大切な印鑑などや日常の物まで、どこに何があるか…と、全く動けなくなったり、生活ができない方が多くいらしゃいます。
親や友達など、大切な人を亡くし悲しみ思うことがあるその時、自分の終活を始めるタイミングなのではないでしょうか。
終活を始めるタイミング6:年金・金融の法改正や会社の体制が変わった時

40代で終活をはじめると、40年後の80歳の時には年金や金融などの法律が改正されていくでしょう。
終活は1回やれば終わりではなく、書き直していいことですし、再度見直すことが必要な事態もあるとおもいます。
年金の受け取り年齢を変更することで、お得な改正もあります。
お金の話は年々変化していきます。
そして、定年退職など会社の体制も変わっていくので、その都度自分にとって有意義である方の選択をしていきます。
年金制度が変わっていく時、終活のスタートとするのも、未来の生活のためにいいタイミングです。
終活を始めるタイミング7:周囲からもめた事例を聞いたとき

親の財産が思った以上にあった…なかった…と、ドラマではありませんが、そのようなもめごとが起きることが多にしてあります。
介護問題によって、家族や兄弟などのもめごともありますね。
周囲では口に出して言わないけれど、高齢化社会で代表的な問題を抱えている方は多いです。
親しい人たちの雑談の中では、もめた事例を聞くことがあると思いますが、親を想う気持ちがあっても、自分の生活に追われていたり、兄弟・お嫁さんなど立場によって考え方が違うので、人間関係がギクシャクしていくのです。
周囲からもめた事例が、自分に当てはまらないのか?と自問自答して、終活を行うことで、少しでもトラブルにならないようにする。
それが、「終活」で大きな成果を得られることです。
終活を始めるタイミング8:親が最期を迎え相続問題が発生したとき
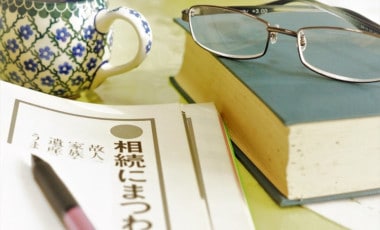
親の相続で、得するばかりではなく“負の遺産”の問題もあります。
一部の財産を受け取ったばっかりに、負の遺産(借金)の責任を負う羽目になることも…。
財産放棄をしなかったばっかりに、人生が狂ってしまうことがあるので、親の申し送りは聞いておくべきなのです。
そして遺産として土地や現金を受け取った後、その使い道やその資産に税金がかかるなど、計画を立てることが大切です。
土地における固定資産税などの出費があることを念頭に、これからのライフスタイルを想像するだけではなく、「終活」で書き残しておくことで、後々自分が最期を迎えた時に、残された人が助かる事柄が多いのです。
終活を始めるタイミング9:子や孫・友人に勧められた時

子どもは親の死後のことを質問しにくいものです。
実際、私も現在同居している88歳の義父に聞きにくいことがあります。
迷惑をかけないように義父は「好きにしていい…」と言いますが、逆にそれが一番大変なんです。
葬式はどの規模?誰を呼ぶ?…と、具体的に聞きにくいのです。
義父は現在スポーツクラブに出かけるほど元気なので、笑いながら少しづつ聞き出している状態です。
率先して「終活」をしてくれたら、それほど嬉しいことはありません。
親族はあなたを心配し、より良い方法で生活し終焉を迎えてほしいと思っているからこそ「終活」を勧めていると、心よく応じてほしいと思います。
終活を始めるタイミング10:テレビや雑誌の特集やエンディングノートに興味を持った時
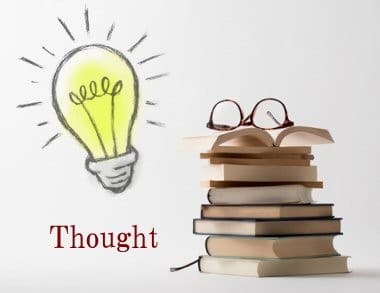
日本政府は2017年9月に「人生100年時代構想」が発足されて、健康的に働き長生きしている世の中になりました。
そんな長い人生を、心身ともに豊かに暮らしていくために、やはり計画を立てたほうがいいよね。
この流れによって、「終活」は未来に向けてよりよい人生を過ごしていくという情報が溢れるようになりました。
まだ自分はそんな年齢ではない…
死んだ後のことは、自由にやってくれ…
…と、残された人に丸投げしていては、残された者が大変です。
愛する人に苦労を残して旅立つよりも、清々しく旅立っていきたいと思っている方は、世に流れる情報に興味をもったと思います。
そう感じた時こと、終活をスタートさせる最も良いタイミングです。
終活は家族や関係者と協力
「今日から終活を始めよう!」と決意した人は、一旦立ち止まってください。
終活は、自分ひとりで迂闊に行ってしまうと、かえって家族や関係者を混乱させてしまうので、結果的に自分自身をも苦しめてしまうことがあります。
エンディングノートに、海にでも散骨してくれ!…だけ書かれていて、残された家族が戸惑う話がありました。
やはり、散骨するのであれば、なぜ散骨してほしいのか?どこに散骨してほしいのか?その費用はどうするのか?など、具体的に書かれていなければ、意に反した結果になりかねません。
エンディングノートに突拍子もないことが書かれていたら「一言も聞いたことがいない!」と、思わぬトラブルを生むことがあります。
家族や施設の関係者など、自分の最期に関わるであろう人に、意思を伝えることが目的ですが、トラブルを生まないためにも、事前に相談することも大切です。
生前整理も協力と理解を得て進めるのがおすすめです。
終活をはじめる3つの心構え

終活をはじめるタイミングには3つのポイントがあります。
- 身体と頭が元気な時に始める
- 節目のタイミングを利用し、万一に備える
- 終活を意識したときに始める
そして、そのタイミングで終活をはじめるには、3つの心構えが必要です。
3つの心構え…気力・体力・判断力です。
死を意識して物事を考え未来を想像して豊かになるために、「気力」がなければ途中で挫折してしまいます。
そして、生前整理は行動を伴うので、「体力」を必要とします。
家具や長年使わなかった古道具の処分や、様々な問題解決などは、椅子に座ってできるものではありませんね。
モノゴトを考えるにあたり、判断・決断を繰り返すことになります。
正しい「判断力」で残された人たちに安心してもらうためです。
老いて認知症がはじまってからの終活は、大きな負担になり正しい判断ができているかが疑問です。
安心できる豊かな生活を後々過ごしていかれるのは、気力・体力・判断力がある時にスタートさせることです。
終活は早めに取り組むことをお勧めします。
・終活とは?自分らしい豊かな人生を修め身支度準備の進め方
・終活の8つの効果|自分の子供が少ない・いない時代だからこそ!
・終活を始める10のタイミングと3つの心構え
・大震災から学んだ大切なこと!自分らしく生きるって何?を考える終活
・50代人生の身支度“終活”のすすめ!自分の未来のため“幸活”に繋げる
・終活を50代前後から始める男女の理由に温度差「修活」で今を修めて豊かな老いを!

“身支度の終活”はじめかた
- 終活とは…
●終活とは?自分らしい豊かな人生を修め身支度準備の進め方
●終活の8つの効果|自分の子供が少ない・いない時代だからこそ!
●自分と大切な人への愛情表現!自分らしく生きてみる!
●「終活のため」様々な角度から情報を提供 - エンディングノートとは
●終活で相続・遺言などを定める「エンディングノート」
●幸を積む未来型「終活ノート」命の五段階活用法エンディングノート
●終活「エンディングノート」具体的な内容と書き方10つのポイント - お金のこと
●終活をして年金・保険・預金・資産をまとめておく必要性
●年金(編集中)
●保険(編集中)
●預金(編集中)
●資産(編集中) - 遠い未来の健康について
●看護・介護・老々介護などはあるものとして考える終活
●看護(編集中)
●介護(編集中)
●老々介護(編集中) - 旅立ち後について
●終活で葬儀・お墓について定めておく
●葬儀(編集中)
●お墓(編集中) - 終活はあなたの未来のために…
●人生100年時代が到来!人生二毛作で楽しむ
●「生きていくため」終活の先にある未来について
●「楽しむため」未来があるから終活をする
●「整えるため」心と身の回りを整える終活